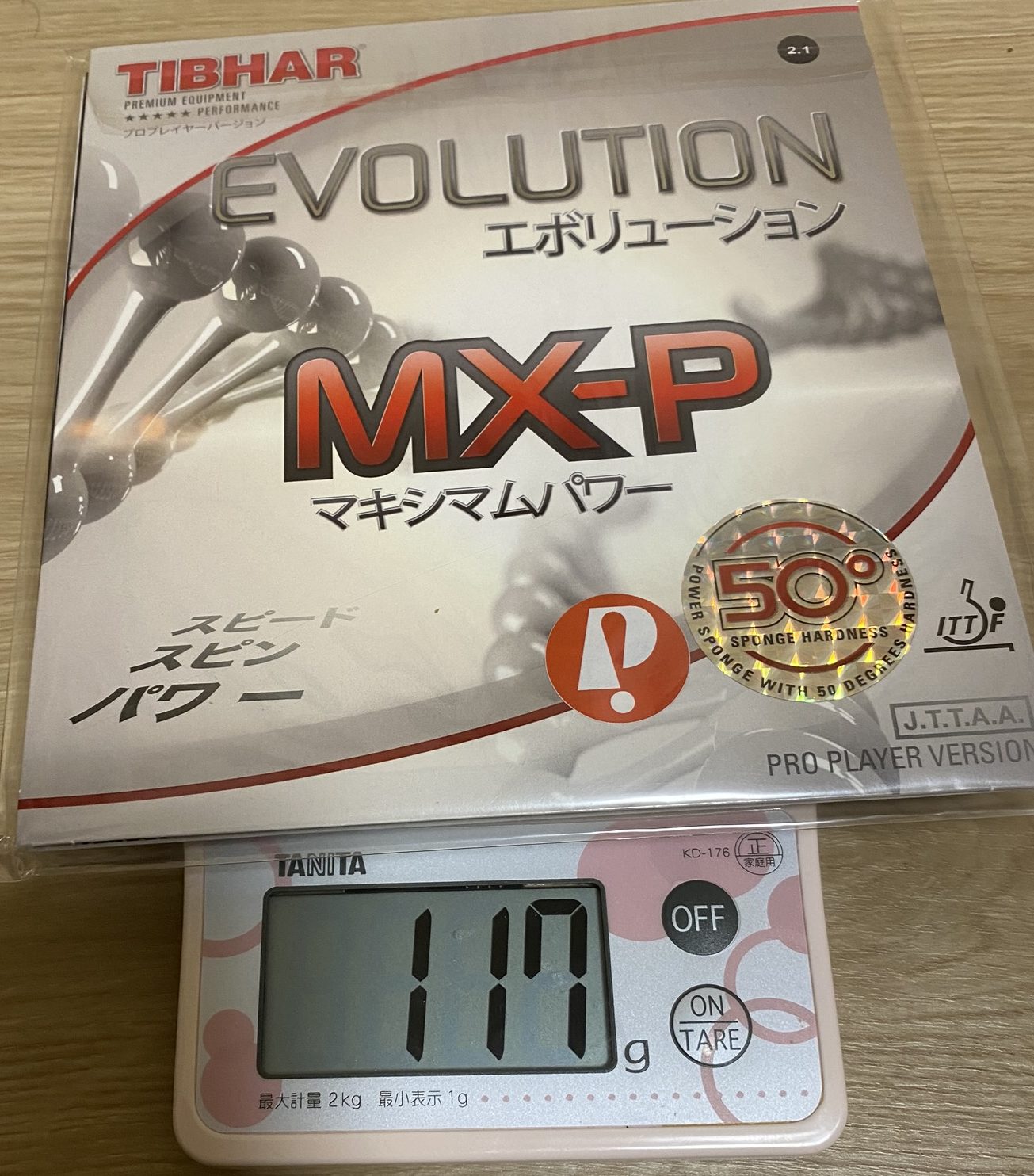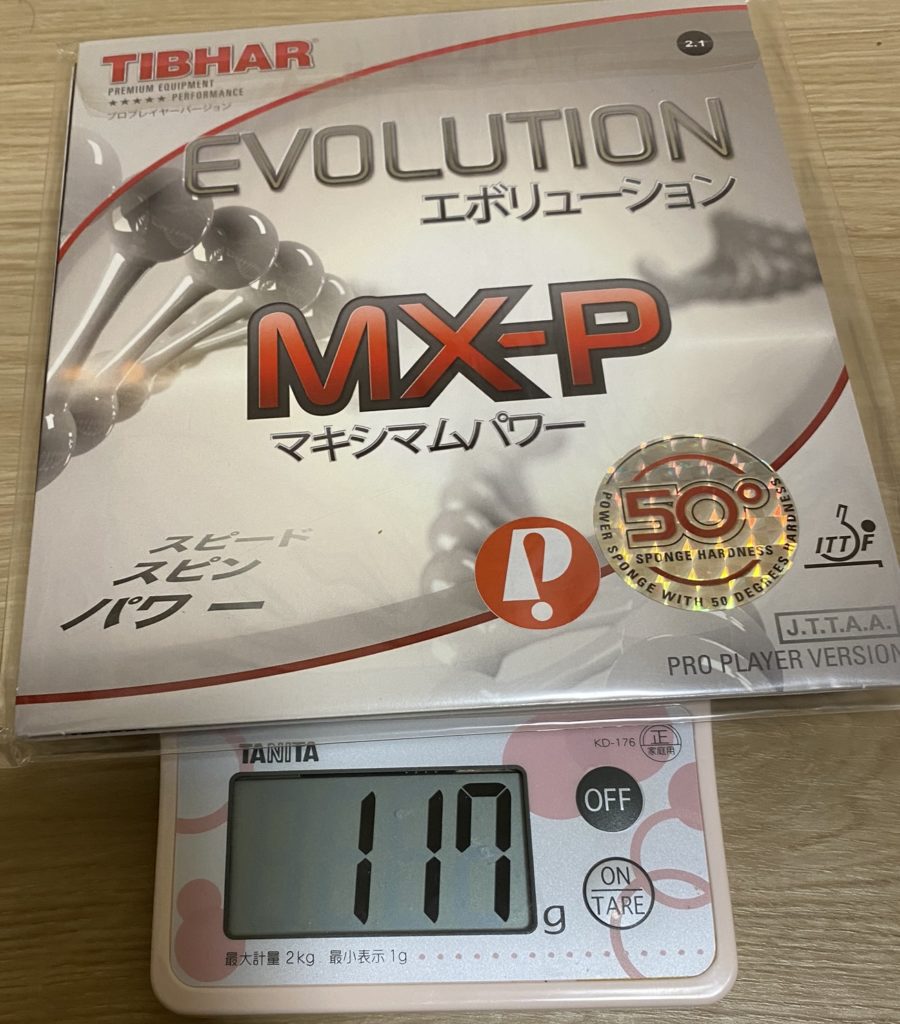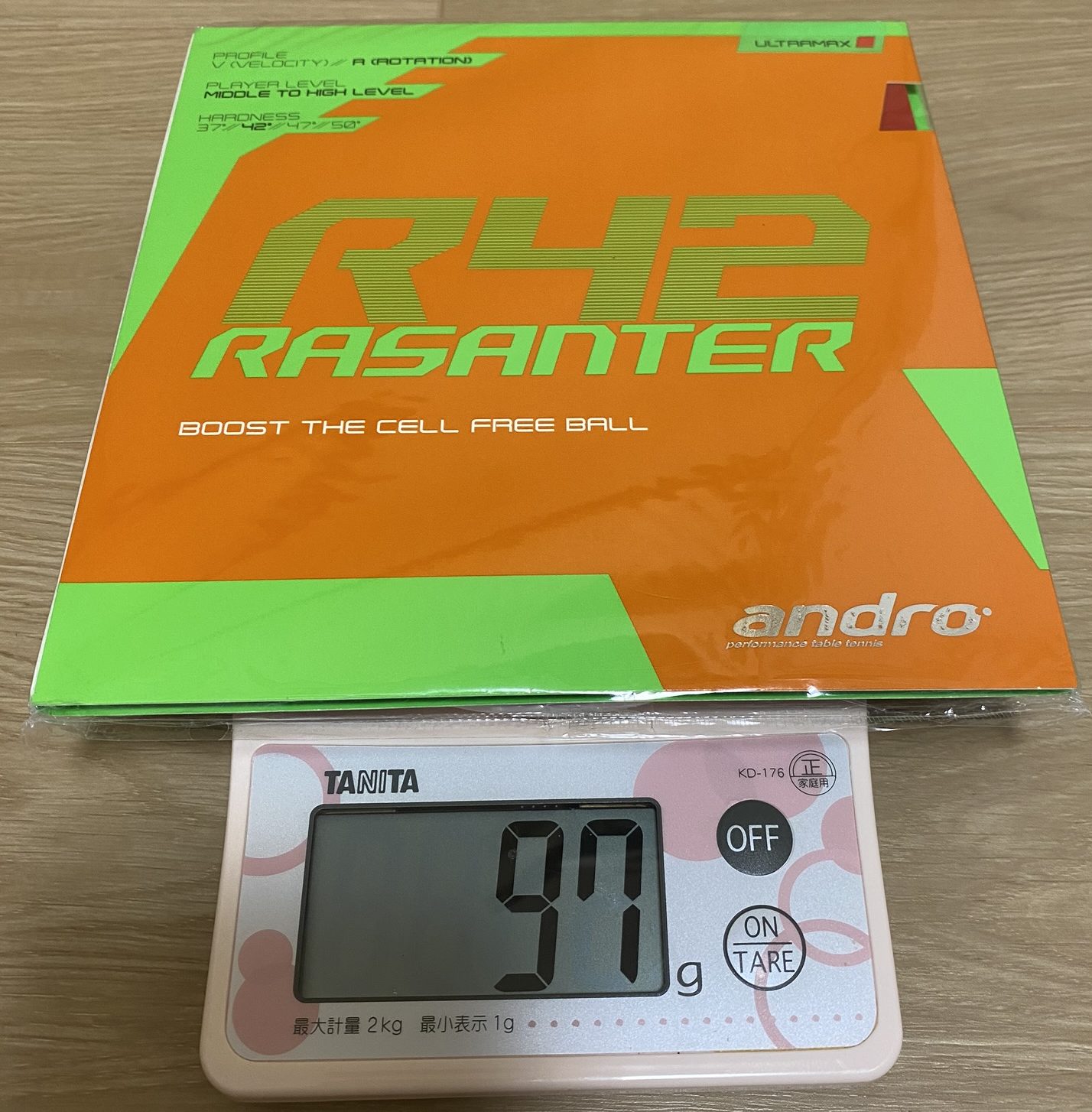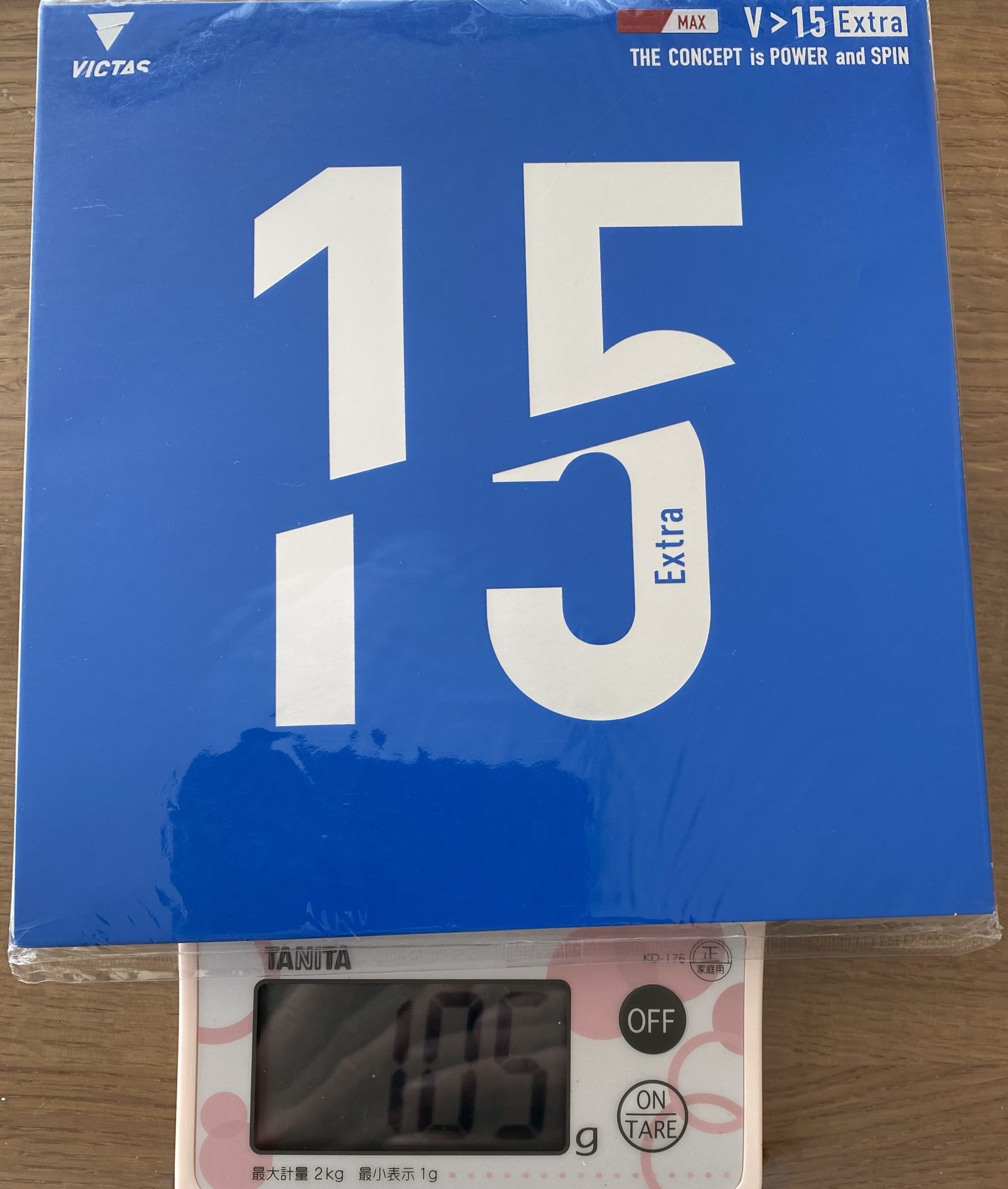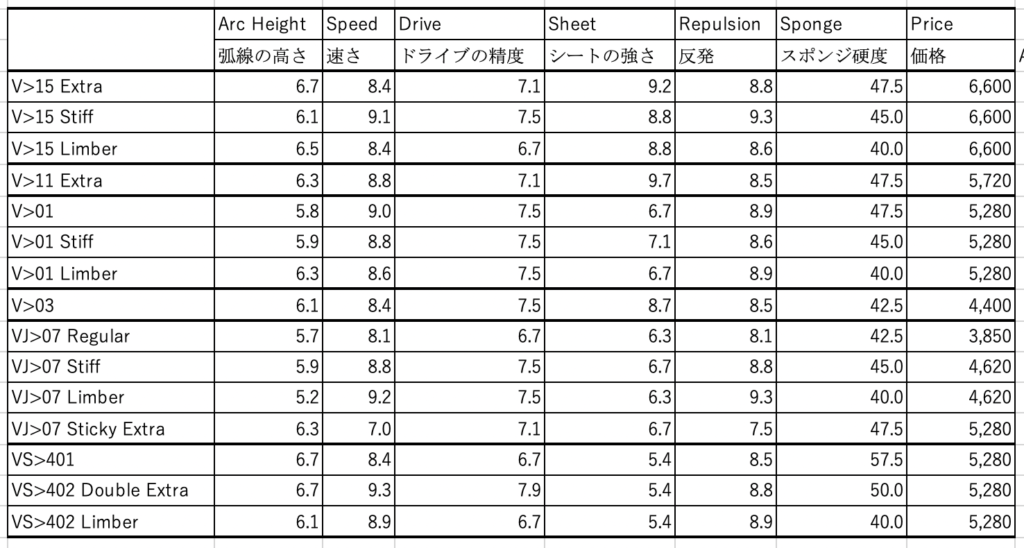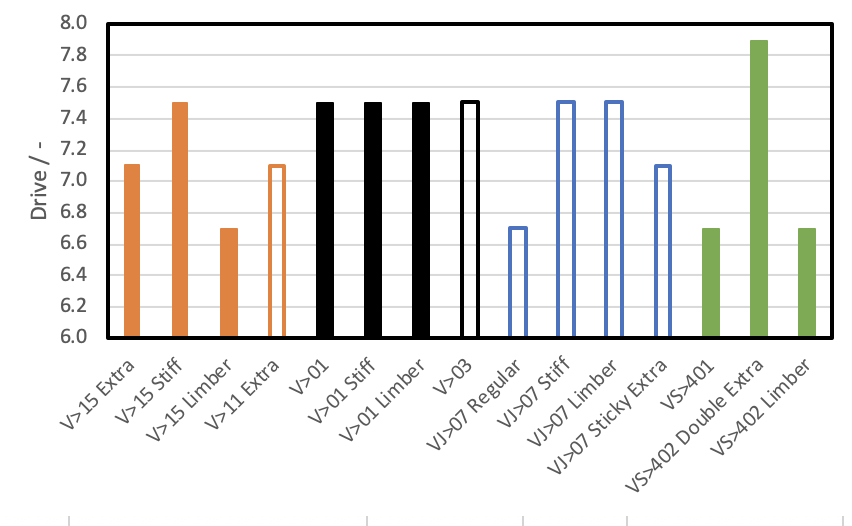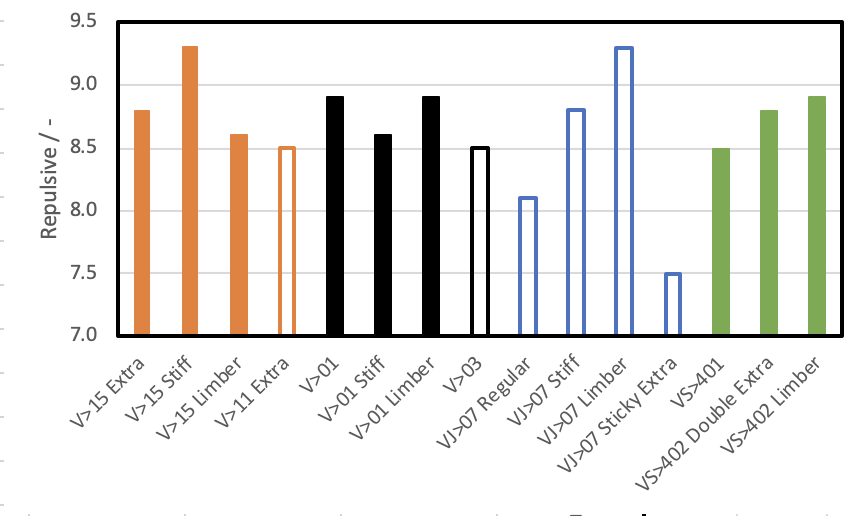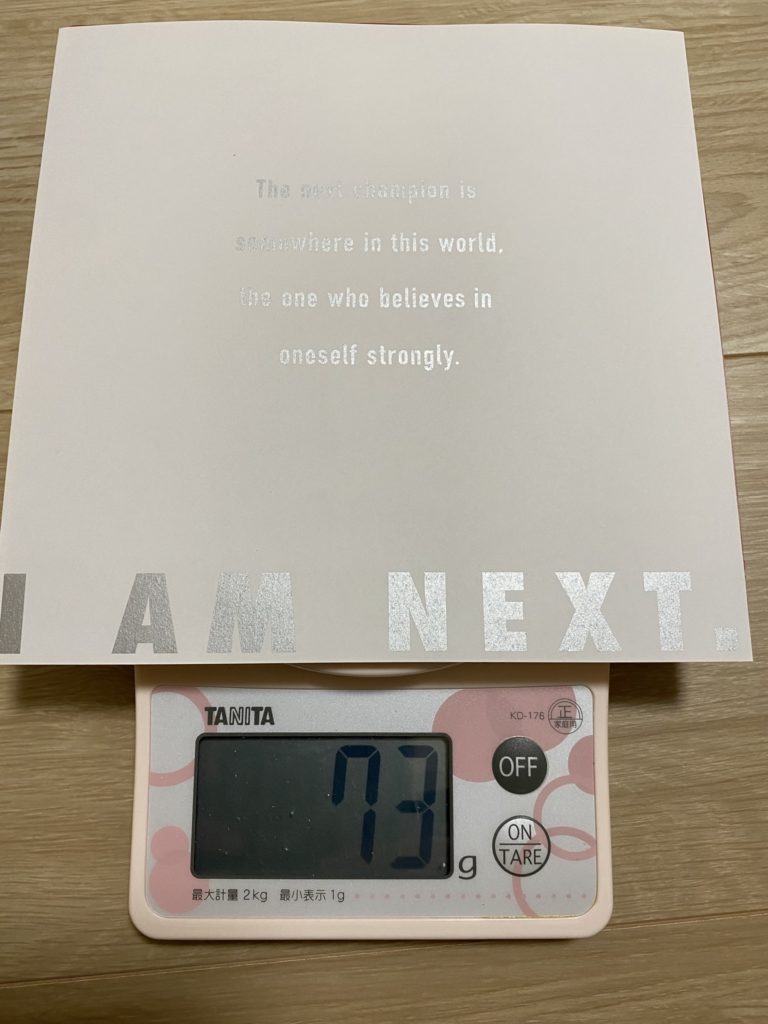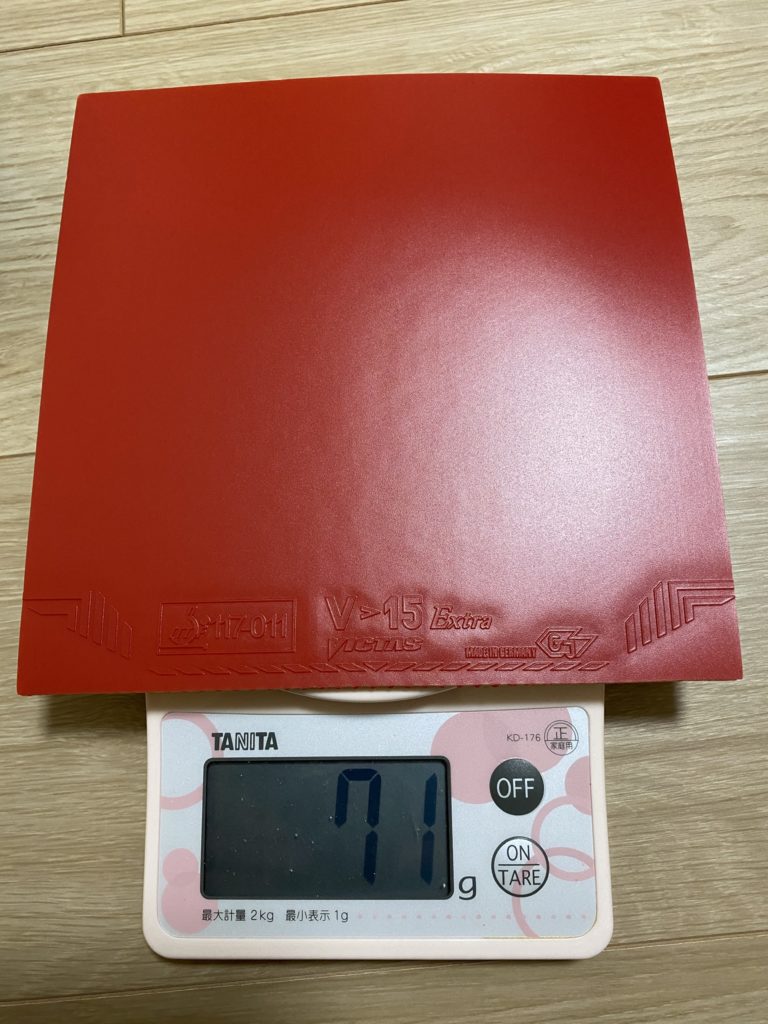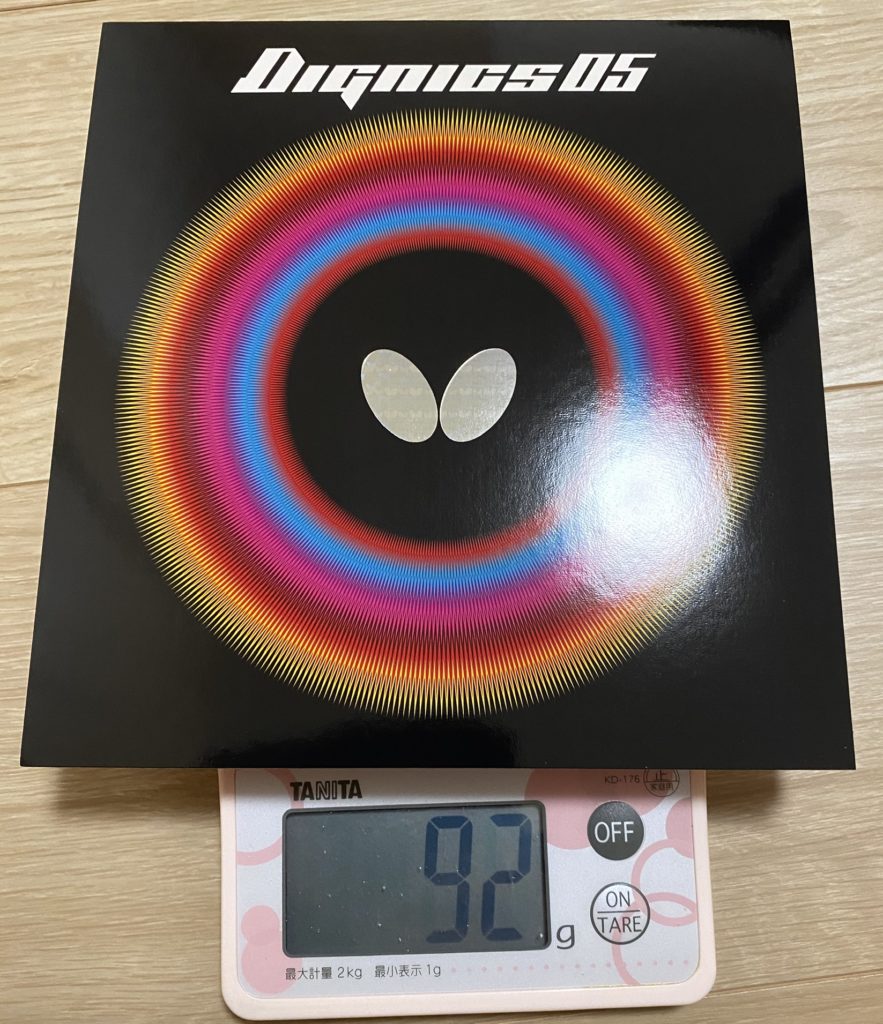バックハンドループドライブのコツ?
結構何度もバックハンドドライブについて記述してきました。(過去のものはLivedoor Blogの方をご覧ください。)で、またかよ感はあるのですが、最近やっとループドライブが打てるようになってきたので書かせていただきます。汗
そもそも何故バックハンドループドライブが難しい?
最近気付いたのですが、バックハンドループドライブはやっぱり難しいですね汗。感覚は掴めてきて、普通のバックハンドドライブならがっつり回転をかけることができた!っていう打球感で打てるようにはなったきたのですが、そのスイングの課題として次のような問題を認識しつつあります。
・インパクト良く打球できる範囲がかなり狭い!
従って前後上下の対応をかなり丁寧にしないといけない。
想像以上にインパクト不足やインパクトする位置ずれが起こりやすい。
これだけであれば、動きを頑張りつつ、無理のない範囲でループドライブをすれば対応はつくと想像するのですが、最近新たな問題が分かりました。それは↓
・ドライブの角度を変更するとインパクトが弱くなったり弾きやすくなったりして難しい!
一番気持ちよく打てる角度は結構角度が寝ている。その角度を変える方法が、フォアの感覚と全然違う、あるいは同じようにやると全然スイングが変わる汗
① フォアハンドドライブでドライブの角度を変えるとき
基本的にはラケット角度を変えていきます。
例)ループドライブなら、ラケットを地面に対して垂直方向に立てる
ラケット角度が変わらないように肘を引いたり膝を曲げたり腰を捻る
スイング中ラケット角度が変わらないようにスイングする
①の方法をバックハンドドライブでやろうとするとかなり難しいことに気付きました。それだけでも1ヶ月以上かかったかも汗
バックハンドドライブ時、ラケットを地面に対して垂直方向に立てる。
ボールの後ろを擦るようにドライブする。
→ ここでセンスのある人は、シートだけに食い込むように薄くとらえる感覚があるのかもしれません。それができるのであれば、自分みたいな難しさを感じないかもしれません。
この①の方法でループドライブをしようとしてかなり頑張ったんですが、コーチをされている方に受けてもらったら全然回転がかかっていないと言われてしまいました涙。(ちなみに、昨年の秋口、自分の感覚が出てきたくらいのドライブは回転がかかっているとおっしゃってくれてました。)アドバイスとしては、もっとラケットを寝かしてボールの上を薄く捉えるようにした方が回転がかかるとおっしゃっていただきました。もう青天の霹靂でしたよ汗。アドバイスの内容的にはループドライブではなくて一般的なバックハンドドライブという意味でおっしゃってくれたのだと思います。
そこで、最近①‘の方法を見つけましたような気がします!
①‘の方法は、やはりバックハンドドライブ時に、ラケット角度を地面に対して垂直にたてます。そこから上方向にスイングするのですが、そうすると腰の回転を使いづらく、手打ちになることもわかってきました。そこで、考えた結果まずまずの質で打てる方法が肘を引くということです。バックハンドループドライブ時に肘を引くようにスイングすることで、ラケットヘッドが円運動しやすくなるとともにバックハンドループドライブとなるようなスイング方向に逆らわないスイングになることがわかってきました。これでもまだ自分のインパクトが弱いので、つまったりすると全然持ち上げられないのですが汗
②の方法が見えてきたかもしれない!
でカーテン打ちをやりまくっていて気付いたのが、腰を落としてバックハンドループドライブすることですね!このスイングを②とさせていただきます。バックスイング時、ラケット角度は結構寝かしておいてOKの方法だと思ってます。バックハンドドライブはスイングしていくと、結構ラケット角度が起きていきやすいスイングになりやすいと思います。ラケット角度が置きやすいことを利用して、または意識的に起こしていってインパクト時にはラケット角度が起きて地面に対して垂直方向に立っているような角度で打球する、というバックハンドループドライブのやり方が②になりますね。起きてきたときに打球するイメージでドライブすると意外とループドライブっぽくなることがわかってきました。そうするとインパクトもまずまず出せてしっかり打てることに気付きましたね。1つの発見だと思いました。
最終的には①‘肘を引く+②腰を落として打球時には面が起きるドライブ
最終的な今のベストだと思うバックハンドループドライブは、①‘+②の打ち方だと思ってます。腰をしっかり落としつつ、①‘の肘を引く打ち方も混ぜることでループドライブとしての質も上がるはずだと想像しています。この方法ならバックスイング完了時にはしっかり面を寝かしていてもバックハンドループドライブはできると思います。
強く感じるのは、フォアハンドドライブと同じような回転の質やスピードのボールをバックハンドドライブでも打てる、しかしながら、同じ体の使い方では、無理がある!と強く思うようになりつつあります。同じボールは打てても同じ打ち方では打てないんですよね!そこが一番大事な気がしています。
以下まとめになります。
1‘ 肘を引く
肘を引いたと同時にボールを離すくらいのイメージなんですが、そうするとループドライブっぽくなりやすい!
2. 腰を落としてラケット面が垂直に立つときに打球する
打球点は落とさずにむしろ顔の前くらいのイメージで、ラケット面が立った時に打球するイメージでバックハンドループドライブするといいですね。ボールの高さと目の高さが同じくらいまで腰を落として打球点は落とさずにループドライブするようにすると打ちやすい気がします。普段のラリーでのバックハンドドライブやレシーブバックハンドドライブではもっと打球点を落としたりするのですが、バックハンドドライブでは打球点を落としすぎるとかなり難しくなります。それは、
A)ラケット角度を起こしてインパクトを出すことが難しい
B)ラケット角度を起こさないてスイングしようとすると、打球面が下を向いているので、そもそも当てることが難しくなる。当たっても、相当のスイングスピードがないと面が寝ているので落ちる。
のA)とB)のために難しくなるのだと思います。よって打球点はあまり落とさない方がいいと感じてきています。
打球点を落としてバックハンドドライブもなしではない
打球点を落とした方が安定すると感じるバックハンドドライブは、レシーブバックハンドドライブになります。レシーブは山をハレることと、いろいろな回転がかかっているため、回転が弱まる打球点が落ちたところを上書きするようにバックハンドドライブする方が安定すると感じています。ただ、ラケット面は寝ていて前方向にスイングするので、ループドライブではないですね。ブチっと真下に切ったサーブは難しいと思います。
最後に
バックハンドドライブは難しいです。毎回練習するごとに打球感覚が変わる感じがありますし、スイングも変わっていってしまうと感じています。この打ち方がベストというものがなかなか掴めなくて日々悶えています。
日本トップ選手の水谷隼選手はバックハンドスピードドライブは打てなくて良いというほどです。それくらい難しい技術と言えるでしょうね。少なくともアマチュアなkatsuo000が言えることは、フォアハンドドライブの時の体の使い方や体の感覚と、バックハンドドライブの時の体の使い方や感覚は全く別!と思って練習に取り組むくらいが良いと思います。
もしご参考いただけるなら、バックハンドループドライブのkatsuo000が思う打ち方は1’ 肘を引くこと、2 打球点はむしろ高くし、ラケット面を起こしてドライブすることがポイントだと思います。ご参考いただければ幸いです。